 古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目) ★古今亭志ん生(五代目)昭和39年(1964年)74歳の映像
志ん生が74歳の時に紫綬褒章を受章した後、NHKのスタジオで「鰍沢」を演じた後のインタビューです。この頃はまだ体調も良く志ん生流の落語論を展開しておりましたが、昭和42(1967)年に勲四等瑞宝章を受章し、その翌年の昭和43(1968)年に...
 古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目) 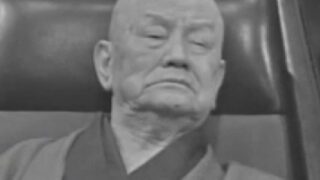 古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目) 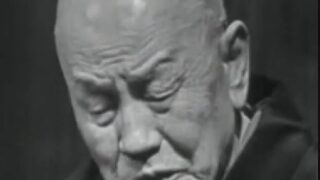 古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  古今亭志ん朝
古今亭志ん朝  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)