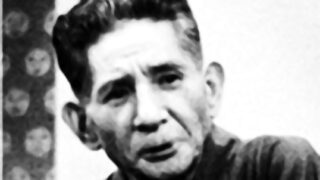 桂三木助(三代目)
桂三木助(三代目) 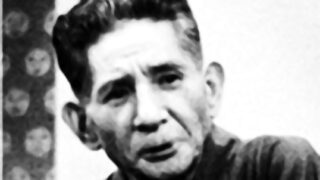 桂三木助(三代目)
桂三木助(三代目)  漫才
漫才 ★夢路いとし・喜味こいし(いとしこいし)ポンポン講談
【お笑い】夢路いとし・喜味こいし 「ポンポン講談」【漫才】
 古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目) ★古今亭志ん生(五代目)文七元結
落語 「文七元結」 古今亭志ん生文七元結(ぶんしち もっとい)は、三遊亭圓朝の創作で、落語のうち、人情噺のひとつ。登場人物が多く、長い演目であり、情の中におかし味を持たせなくてはならないという理由から、難しい一題とされ、逆に、これができれば...
 春風亭昇太
春風亭昇太 ★春風亭昇太/看板のピン
【落語】春風亭昇太『看板のピン』
 春風亭柳好(三代目)
春風亭柳好(三代目) ★春風亭柳好(三代目)たいこ腹(幇間腹・太鼓腹)
春風亭柳好(三代目)たいこ腹(幇間腹・太鼓腹)【歴史的音源】たいこ腹(たいこばら)は、古典落語の演目の一つ。別題は『幇間腹』。原話は、安永9年(1780年)年に出版された笑話本『初登』の一編である「針医」元々は上方落語の演目で、主な演者には...
 古今亭志ん朝
古今亭志ん朝 ★古今亭志ん朝/もう半分
「もう半分」(もうはんぶん)は、落語の演目の一つで怪談話。別名「五勺酒」。主な演者は五代目古今亭今輔や五代目古今亭志ん生等。演者によって舞台が違い(詳しくは後述)、それによって多少話の流れも変わる。以下のあらすじは永代橋を舞台とする版のあら...
 古今亭志ん朝
古今亭志ん朝 ★古今亭志ん朝/寝床
あらすじある商家のだんな、下手な義太夫に凝っている。それも人に聴かせたがるので、皆迷惑。今日も、家作の長屋の連中を集めて自慢のノドを聞かせようと大張りきり。番頭の茂造に長屋を回って呼び集めさせ、自分は小僧の定吉に、晒に卵を買ってこい、お茶菓...
 古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目) ★古今亭志ん生(五代目)庚申待(こうしんまち)~宿屋の仇討
庚申待(頭山バージョン) 古今亭志ん生宿屋仇(やどやがたき)は上方落語の演目の一つ。「日本橋宿屋仇」とも言う。東京では「宿屋の仇討」「庚申待」「甲子待」との演目名で演じられる。大阪では5代目笑福亭松鶴、3代目桂米朝が、東京では3代目桂三木助...
 三遊亭圓生(六代目)
三遊亭圓生(六代目) ★三遊亭圓生(六代目)ねずみ穴(鼠穴)
落語 「鼠穴」 三遊亭圓生川柳川柳が落語家になろうと師匠と決めた縁の一席でございます。あらすじ亡くなった父の遺した田畑を二等分した百姓の兄弟。金に換えた兄はそれを元手に江戸へ出て成功し大店を持つようになる。一方、弟は遊びで全てを使い果たし...
 古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目) ★古今亭志ん生(五代目)五目講釈
上方では「居候講釈」の演題が使われる。志ん生は一時、三代目小金井蘆洲(小金井芦州)門下の講釈師になったことがあるので、講釈は口慣れている。ラジオによく出していて、『調合』の題でやったこともある。昭和33年(1958)6月15日にニッポン放送...
 三遊亭圓生(六代目)
三遊亭圓生(六代目) ★三遊亭圓生(六代目)しの字嫌い・紙入れ
落語 「しの字嫌い/紙入れ」 三遊亭圓生しの字嫌い(しのじぎらい)は古典落語の演目の一つ。上方落語ではしの字丁稚(しのじでっち)。上方の『正月丁稚』(東京では『かつぎや』)の前半部分が独立したもの。原話は、明和5年(1768年)に出版され...
 三遊亭圓生(六代目)
三遊亭圓生(六代目) ★三遊亭圓生(六代目)妾馬(八五郎出世)
落語 「妾馬 」三遊亭圓生八五郎出世(はちごろうしゅっせ)は古典落語の演目の一つ。別題は『妾馬』(めかうま)。主な演者として、5代目古今亭志ん生や3代目古今亭志ん朝、10代目金原亭馬生、6代目三遊亭圓生、上方では桂文太などがいる。圓生の「八...
 三遊亭圓生(六代目)
三遊亭圓生(六代目) ★三遊亭圓生(六代目)初音の鼓
落語 「初音の鼓」 三遊亭圓生あらすじさる殿様のお城に使える三太夫は、来る度に殿に胡散臭いものを売りつける古商人の吉兵衛のことが気に入らないでいる。すると、そこへその吉兵衛が懲りずにやってきて、今度は「初音の鼓」という品を持ってきたという。...
 漫才
漫才 ★夢路いとし・喜味こいし(いとしこいし)我が家の湾岸戦争
夢路いとし・喜味こいし「我が家の湾岸戦争」
 三遊亭金馬(三代目)
三遊亭金馬(三代目) ★三遊亭金馬(三代目)随談艶笑見聞録
 春風亭昇太
春風亭昇太 ★春風亭昇太/力士の春
落語 「力士の春」 春風亭昇太
 三遊亭圓生(六代目)
三遊亭圓生(六代目) ★三遊亭圓生(六代目)やかん(薬缶)
落語 「やかん」 三遊亭圓生あらすじこの世に知らないものはないと広言する隠居。長屋の八五郎が訪ねるたびに、別に何も潰れていないが、グシャ、グシャと言うので、一度へこましてやろうと物の名の由来を次から次へ。ところが隠居もさるもの、妙てけれん...
 三遊亭金馬(三代目)
三遊亭金馬(三代目) ★三遊亭金馬(三代目)長屋の花見(貧乏花見)
落語 「長屋の花見」 三遊亭金馬「貧乏花見は落語の演目。元々は上方落語の演目の一つである。江戸落語では「長屋の花見」。上方では、初代桂春團治、5代目笑福亭松鶴、6代目笑福亭松鶴、3代目桂米朝、2代目桂枝雀、3代目笑福亭仁鶴。東京では、3代目...
 古今亭志ん朝
古今亭志ん朝 ★古今亭志ん朝/堀の内
堀の内(堀之内)は古典落語の演目の一つ。粗忽(あわて者)を主人公とした小咄をいくつもつなげて一つにしたオムニバス形式の落語であるため、噺家によっては最後までやらずに途中でサゲることも多い。上方落語、いらちの愛宕詣り(いらちのあたごまいり)が...
 三遊亭圓生(六代目)
三遊亭圓生(六代目) ★三遊亭圓生(六代目)突き落とし(上方版~棟梁の遊び)
大人のニコニコ落語「突き落し」三遊亭圓生文化年間(1804~18)から伝わる江戸廓噺。原話不詳。大正期には、初代柳家小せんの速記が残っている。戦後では三代目桂三木助の十八番。現在では、柳家三三ほか、若手も演じるようになった。上方版では、『棟...