 古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目) ★古今亭志ん生(五代目)安兵衛狐
あらすじ六軒長屋があり、四軒と二軒に分かれている。四軒の方は互いに隣同士で仲がよく、二軒の方に住んでいる「偏屈の源兵衛」と「ぐずの安兵衛」、通称グズ安も仲がいい。ところが、二つのグループは犬猿の仲。ある日、四軒の方の連中が、亀戸に萩を見に繰...
 古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  露の五郎兵衛(二代目)
露の五郎兵衛(二代目)  立川談志
立川談志  柳家小さん(五代目)
柳家小さん(五代目)  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  コラム
コラム 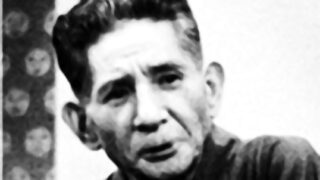 桂三木助(三代目)
桂三木助(三代目) 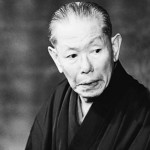 林家彦六(八代目 林家正蔵)
林家彦六(八代目 林家正蔵) 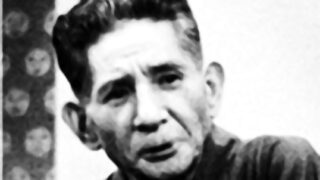 桂三木助(三代目)
桂三木助(三代目) 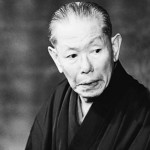 林家彦六(八代目 林家正蔵)
林家彦六(八代目 林家正蔵) 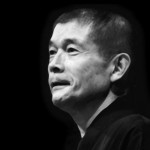 柳家小三治(十代目)
柳家小三治(十代目) 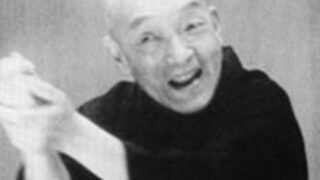 三遊亭百生(二代目)
三遊亭百生(二代目)  露の五郎兵衛(二代目)
露の五郎兵衛(二代目)  露の五郎兵衛(二代目)
露の五郎兵衛(二代目) 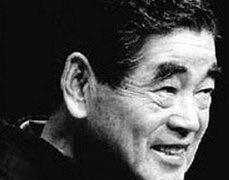 春風亭柳好(四代目)
春風亭柳好(四代目)  露の五郎兵衛(二代目)
露の五郎兵衛(二代目)  桂小南(二代目)
桂小南(二代目)  柳家三三
柳家三三 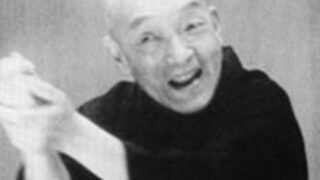 三遊亭百生(二代目)
三遊亭百生(二代目) 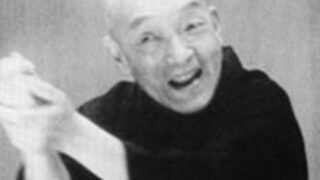 三遊亭百生(二代目)
三遊亭百生(二代目)