 三遊亭圓生(六代目)
三遊亭圓生(六代目) ★三遊亭圓生(六代目)三年目
三年目(さんねんめ)は古典落語(江戸落語)の演目の一つ。4代橘家圓喬(たちばなやえんきょう、1865年~1912年)が得意とした噺で、5代三遊亭円生(さんゆうていえんしょう、1884年~1940年)、6代三遊亭円生(1900年~1979年)...
 三遊亭圓生(六代目)
三遊亭圓生(六代目)  三遊亭圓生(六代目)
三遊亭圓生(六代目)  三遊亭圓生(六代目)
三遊亭圓生(六代目)  三遊亭圓生(六代目)
三遊亭圓生(六代目)  三遊亭圓生(六代目)
三遊亭圓生(六代目)  三遊亭圓生(六代目)
三遊亭圓生(六代目)  三遊亭圓生(六代目)
三遊亭圓生(六代目)  三遊亭圓生(六代目)
三遊亭圓生(六代目)  三遊亭圓生(六代目)
三遊亭圓生(六代目)  三遊亭圓生(六代目)
三遊亭圓生(六代目)  三遊亭圓生(六代目)
三遊亭圓生(六代目) 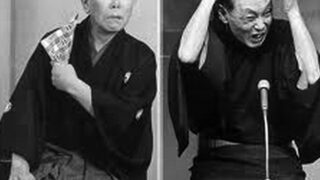 三遊亭圓生(六代目)
三遊亭圓生(六代目)  三遊亭圓生(六代目)
三遊亭圓生(六代目)  三遊亭圓生(六代目)
三遊亭圓生(六代目)