 おもしろ
おもしろ ラバーハンド錯覚/ラバーハンドイリュージョン(rubber hand illusion)
ラバーハンド実験【おもしろ動画】ラバーバンド錯覚ヒトは自分の身体を毎日のように見て、数え切れぬほど触り、身体から多くの情報を得ている。自分自身の身体について相当な情報を収集しているに違いないが、それにも関わらず、ヒトは自分の身体について多く...
 おもしろ
おもしろ  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  立川談笑(六代目)
立川談笑(六代目)  立川談志
立川談志  金原亭馬生(十代目)
金原亭馬生(十代目)  立川談志
立川談志  桂文楽(八代目)
桂文楽(八代目)  桂文楽(八代目)
桂文楽(八代目) 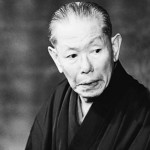 林家彦六(八代目 林家正蔵)
林家彦六(八代目 林家正蔵) 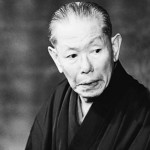 林家彦六(八代目 林家正蔵)
林家彦六(八代目 林家正蔵)  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  柳家小さん(五代目)
柳家小さん(五代目)  露の五郎兵衛(二代目)
露の五郎兵衛(二代目) 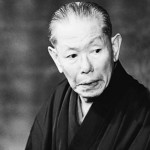 林家彦六(八代目 林家正蔵)
林家彦六(八代目 林家正蔵) 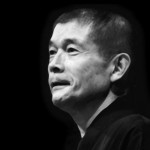 柳家小三治(十代目)
柳家小三治(十代目) 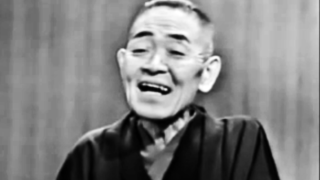 三笑亭可楽(八代目)
三笑亭可楽(八代目)  古今亭右朝
古今亭右朝  古今亭右朝
古今亭右朝  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  三遊亭圓橘(三代目)
三遊亭圓橘(三代目)