 古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目) ★古今亭志ん生(五代目)唐茄子屋政談・心中時雨傘
あらすじ根津権現の祭りは勇壮だった。祭りの準備で屋台が出て、その上根津の遊廓の賑わいもすごかった。縁日の屋台の、ドッコイ屋と言うのがあった。ドッコイ屋は盤の中央に回転する棒がついていて、その先に針があってマス目の中に景品が書いてあり、当たる...
 古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  三遊亭圓生(六代目)
三遊亭圓生(六代目)  三遊亭圓生(六代目)
三遊亭圓生(六代目)  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目) 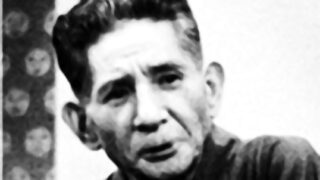 桂三木助(三代目)
桂三木助(三代目)  古今亭志ん朝
古今亭志ん朝  古今亭志ん朝
古今亭志ん朝  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  古今亭志ん朝
古今亭志ん朝  古今亭志ん朝
古今亭志ん朝 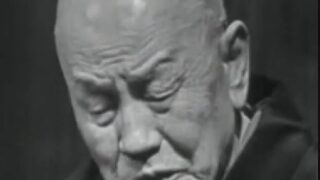 古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  三遊亭圓生(六代目)
三遊亭圓生(六代目)  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目) 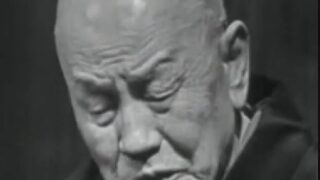 古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  立川談志
立川談志  金原亭馬生(十代目)
金原亭馬生(十代目)  金原亭馬生(十代目)
金原亭馬生(十代目)  三遊亭金馬(三代目)
三遊亭金馬(三代目)  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目) 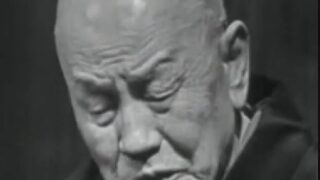 古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)