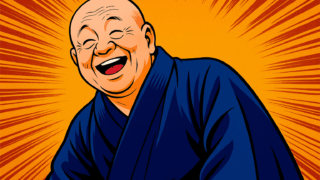 雑学・豆知識
雑学・豆知識 ★古今亭志ん生(五代目)氏子中(町内の若い衆)/金原亭馬生(七代目)時代の歴史的音源《風俗雑学豆知識》
七代目金原亭馬生時代の音源:昭和10年(1935年)2月発売SP盤(当時44歳)七代目金原亭馬生襲名:1934年(昭和9年)五代目古今亭志ん生襲名:1939年(昭和14年)あらすじ氏子中(うじこじゅう)ある日、商用で出かけた亭主が出先から帰...
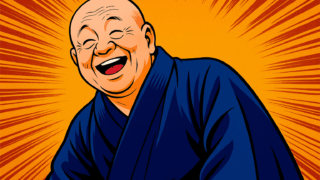 雑学・豆知識
雑学・豆知識  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)