 三遊亭圓生(六代目)
三遊亭圓生(六代目) ★三遊亭圓生(六代目)首提灯【芸術祭文部大臣賞受賞】
首提灯(くびぢょうちん)は古典落語の演目の一つ。原話は、安永3年(1774年)に出版された笑話本・「軽口五色帋」の一遍である『盗人の頓智』。近年の主な演者には、4代目橘家圓蔵や6代目三遊亭圓生(この噺で芸術祭文部大臣賞受賞)、そして林家彦六...
 三遊亭圓生(六代目)
三遊亭圓生(六代目) 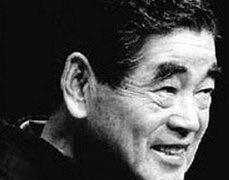 春風亭柳好(四代目)
春風亭柳好(四代目)  立川談志
立川談志  三遊亭圓生(六代目)
三遊亭圓生(六代目) 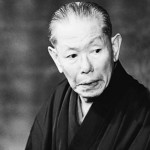 林家彦六(八代目 林家正蔵)
林家彦六(八代目 林家正蔵)  柳家小さん(五代目)
柳家小さん(五代目) 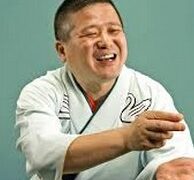 三遊亭白鳥
三遊亭白鳥  桂文楽(八代目)
桂文楽(八代目) 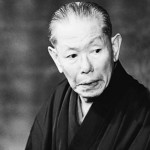 林家彦六(八代目 林家正蔵)
林家彦六(八代目 林家正蔵)  三遊亭圓生(六代目)
三遊亭圓生(六代目)  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目) 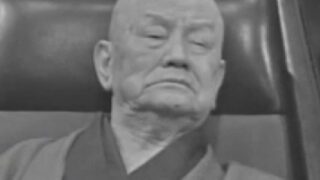 古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目) 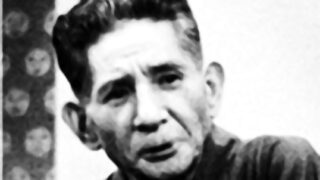 桂三木助(三代目)
桂三木助(三代目) 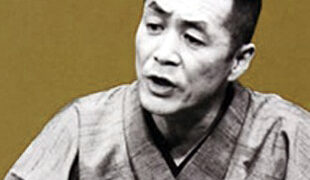 入船亭扇橋(九代目)
入船亭扇橋(九代目)  立川談志
立川談志 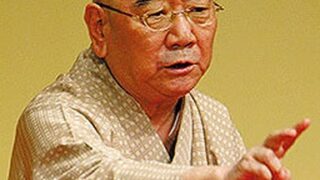 三遊亭圓歌(三代目)
三遊亭圓歌(三代目)  桂文楽(八代目)
桂文楽(八代目)  桂文楽(八代目)
桂文楽(八代目)  立川談志
立川談志  柳家小さん(五代目)
柳家小さん(五代目)