 三遊亭圓生(六代目)
三遊亭圓生(六代目)  三遊亭圓生(六代目)
三遊亭圓生(六代目)  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目) ★古今亭志ん生(五代目)疝気の虫
疝気の虫(せんきのむし)は古典落語の演目の一つ。原話は、寛政8年に出版された笑話本・「即答笑合」の一遍である『疝鬼』。主な演者には、初代三遊亭遊三や5代目古今亭志ん生、桂雀々などがいる。あらすじ変な虫を見つけた医者。つぶそうとすると、なんと...
 古今亭志ん朝
古今亭志ん朝 ★古今亭志ん朝/おかめ団子
 立川談志
立川談志 ★立川談志/死神
 三遊亭圓遊(四代目)
三遊亭圓遊(四代目) ★三遊亭圓遊(四代目)夏泥(置泥おきどろ)
置泥(おきどろ)は、古典落語の演目の一つ。原話は、安永7年(1778年)に出版された笑話本『気の薬』の一遍である「貧乏者」。別題として「夏泥」。元々は『打飼盗人』という上方落語の演目で、大正末期に初代柳家小はんが東京に移植した。原話は、忍び...
 金原亭馬生(十代目)
金原亭馬生(十代目) ★金原亭馬生(十代目)吝い屋(しわい屋)
 桂文楽(八代目)
桂文楽(八代目) ★桂文楽(八代目)按摩の炬燵
あらすじ冬の寒い晩、出入りの按摩(あんま)に腰を揉ませている、ある大店の番頭。「年を取ると寒さが身にこたえる」とこぼすので、按摩が「近ごろは電気炬燵という、けっこうなものが出てきたのに、おたくではお使いではないんですかい」と聞くと「若い者は...
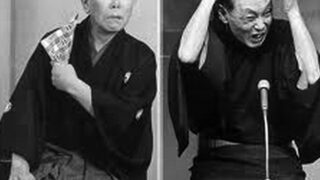 三遊亭圓生(六代目)
三遊亭圓生(六代目) ★【リレー落語】三遊亭圓生~林家正蔵【真景累ヶ淵】
 三遊亭圓生(六代目)
三遊亭圓生(六代目) ★三遊亭圓生(六代目)水神
水神は、1963年(昭和38)劇作家・作詞家:菊田一夫が六代目三遊亭圓生のために書き下ろした新作落語。1963年11月15日の芸術祭参加第53回東京落語会で初演している。あらすじ三廻りの縁日でございまして、大変、人が出盛っている。銀杏の葉が...
 春風亭昇太
春風亭昇太 ★春風亭昇太/人生が二度あれば
落語 人生が二度あれば 春風亭昇太一心不乱に働き、気が付いた時には老齢期。縁側で趣味の盆栽に手を入れながら、もう一度人生をやりなおせたら。と人生を振り返り返っていると……
 その他
その他 ★立川錦之助(ビートたけし)わっ道具屋だ
【落語】 ビートたけし 「わっ道具屋だ」北野武立川流Bコースに入門して「立川錦之助」の名を受ける。Bコースは落語家になるためのコースではなかったため実際に談志師匠が稽古を付ける事はなかった。1983年の立川流創設直後から名を連ねている。
 古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目) ★古今亭志ん生(五代目)佃祭(つくだまつり)
佃祭(つくだまつり)は、落語の演目の一つ。住吉神社の夏の祭礼で賑わう佃島を舞台に、「情けは人の為ならず」という諺をテーマとした江戸落語である。主な演者は五代目古今亭志ん生、三代目三遊亭金馬である。志ん生は長屋の騒動を強調して喜劇調に演じてい...
 立川談志
立川談志 ★立川談志/馬の田楽(うまのでんがく)
1968年(昭和43年)4月:録音あらすじ頼まれた味噌の荷を馬に積んで三州屋という酒屋に来た男。いくら呼んでも誰も出て来ないので、馬を道端につないで待っているうち、居眠りをしてしまう。目をさますと店の者がいるので、味噌を持ってきたというとう...
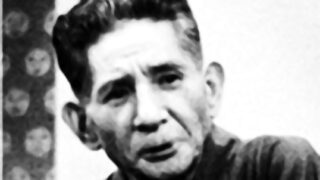 桂三木助(三代目)
桂三木助(三代目) ★桂三木助(三代目)蛇含草
上方落語発祥の古典落語で、大食いを自慢する男と謎の薬草をめぐる滑稽噺。主な演者に上方の2代目桂枝雀、東京の4代目三遊亭圓生、2代目桂小金治、2代目桂文朝らが知られる。蛇眼草とも表記する。東京で演じられる「そば清」は、三代目桂三木助が、上方の...
 立川談志
立川談志 ★立川談志/蔵前駕籠(くらまえかご)
国立演芸場 談志ひとり会 ラスト・デイズ131999年(平成11年)4月8日
 春風亭柳朝(五代目)
春風亭柳朝(五代目) ★春風亭柳朝(五代目)一眼国(いちがんこく)
落語 「一眼国」 五代目春風亭柳朝あらすじ諸国をまわり歩く六部(ろくぶ)が、香具師の親方のところに一晩の宿を借りた。香具師は何か変わった人間でもいれば、いや化物ならなおさらいいが、とにかく捕まえて見世物にし、金もうけの種にしようと八方手を尽...
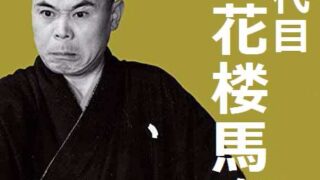 蝶花楼馬楽(六代目)
蝶花楼馬楽(六代目) ★蝶花楼馬楽(六代目)短命(長命)
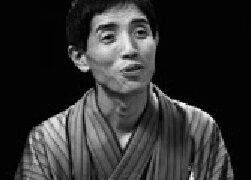 桂春蝶(二代目)
桂春蝶(二代目) ★桂春蝶(二代目)鉄砲勇助(嘘つき村)
 柳家権太楼(三代目)
柳家権太楼(三代目) ★柳家権太楼(三代目)くしゃみ講釈
 古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目) ★古今亭志ん生(五代目)浜野矩隨(はまののりゆき:名工矩隨)
1956年(昭和31年)録音浜野矩隨は、江戸中期の装剣金工家。通称を忠五郎、江戸神田小柳町に住したといい、浜野政随の門下で学ぶ。15歳から17歳ごろ、師から矩随の名を許された。浜野の苗字は師の流名を許されたもの。蓋雲堂・望窓軒・青柳軒・生寿...