あらすじ
明和3(1766)年のこと。
苦労の末、名題に昇進にした中村仲蔵は、「忠臣蔵」五段目の定九郎役をふられた。
あまりいい役ではない。
五万三千石の家老職、釜九太夫のせがれ定九郎が、縞の平袖、丸ぐけの帯を締め、山刀を差し、ひもつきの股引をはいて五枚わらじ。
山岡頭巾をかぶって出てくるので、どう見たって山賊の風体。
これでは、だれも見てくれない。
そこで仲蔵、「こしらえに工夫ができますように」と、柳島の妙見さまに日参した。
満願の日。
参詣後、雨に降られて法恩寺橋あたりのそば屋で雨宿りしていると、浪人が駆け込んできた。
年のころは三十二、三。
さかやきが森のように生えており、黒羽二重の袷(あわせ)の裏をとったもの、これに茶献上の帯。
艶消し大小を落とし差しに尻はしょり、茶のきつめの鼻緒の雪駄を腰にはさみ、破れた蛇の目をポーンとそこへ放りだす。
さかやきをぐっと手で押さえると、たらたらとしずくが流れるさま。
この姿に案を得た仲蔵は、拝領の着物が古くなった感じを出すべく、黒羽二重を羊羹色にし、帯は茶ではなく白献上、大小は艶消しではなく舞台映えするように朱鞘、山崎街道に出る泥棒が雪駄ではおかしいので福草履に変えて、こしらえが完成。
初日は、出番になる直前に手桶で水を頭からかけ、水のたれるなりで見得(みえ)を切った。
初日の客は、あまりの出来にわれを忘れ、ただ息をのむばかり。
場内は水を打ったような静けさ。
これを悪落ちしたと勘違いした仲蔵は、葭町の家に戻り、
「もう江戸にはいられない。上方に行くぜ」
と女房のおきしに旅支度をととのえさせる始末。
そこへ、師匠の中村伝九郎から呼ばれる。
行ってみると、師匠は仲蔵の工夫をほめたばかりか、仲蔵の定九郎の評判で客をさばくのに
表方がてんてこまいしたとのこと。
これをきっかけに芸道精進した中村仲蔵は、名優として後世に名を残したという話。
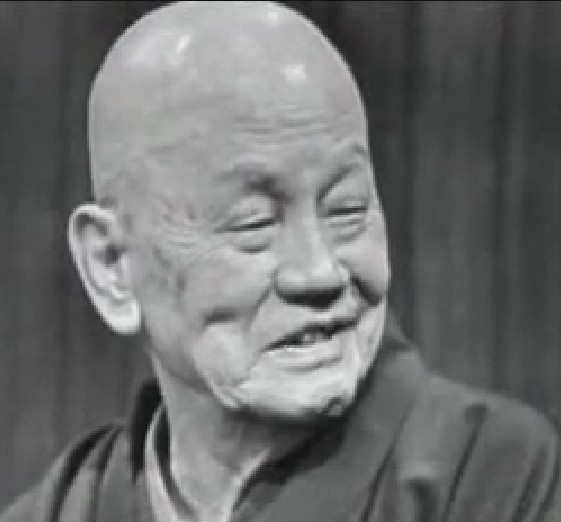


コメント