Z世代発信力:SNS発の言葉がトレンドを牽引~消費文化の種はユーザーから生まれる時代~Z世代の遊び心がマーケティングを超えた
ぼくはこの数年で、「トレンドの生まれる場所」が劇的に変わったと感じています。
昔はテレビや雑誌、芸能人が「次に流行るのはコレです!」と宣言して、ぼくらはそれを追いかけていました。でも今は、逆です。TikTokやTwitter(X)、Instagramにポロっと出てきた言葉や動画から、あっという間に全国区のトレンドが生まれます。
たとえば「きゅんです」ポーズ。最初はTikTokで数人が投稿しただけでしたが、数週間後には芸能人やアイドルが真似し、CMや雑誌にまで広がりました。気づけば「国民的ポーズ」みたいに扱われていました。
つまり、消費文化の出発点は企業ではなく、ぼくらユーザーの発信になったのです。今日はその流れを、実際のSNSの事例を交えながら掘り下げます。

Z世代がSNSで放つ言葉の力
Z世代が放つ言葉は、なぜこんなにも人を惹きつけるのでしょうか。
一番大きい理由は「使う場所がSNSだから」です。SNSは日常と直結しているので、共感が広がるスピードが恐ろしく速いのです。
例えばTwitterで「#ぴえん」が流行ったとき。最初は一部の学生が「泣きたい気持ち」を短く可愛く表現するために使い始めただけでした。でもその言葉が一気に拡散し、数か月後には「ぴえんこえてぱおん」なんて派生語まで誕生。さらに「ぴえん」をモチーフにしたスマホゲームまで登場し、完全にカルチャー化しました。

Instagramでも同じです。ある女子大生が「おしゃピク(おしゃれピクニック)」とタグ付けして投稿した写真が話題になり、全国の若者が真似をして「映えるピクニック」をシェアするようになりました。すると100均や雑貨店が「ピクニック映えグッズ」を売り出し、企業まで巻き込んだブームになりました。

このように、Z世代の一言やアイデアは、SNSを通じて一瞬で共有され、次の瞬間にはカルチャーに昇格してしまうのです。
消費文化をひっくり返す「逆流現象」
従来の流行は、テレビや広告会社がつくっていました。流れは「企業が商品を用意 → メディアが紹介 → 消費者が買う」。
でも今は真逆です。ユーザーが発信 → SNSでバズる → 企業が後から商品化する。この逆流現象があたりまえになっています。
TikTokで「チャレンジ動画」が広まると、アーティストはそれを公式に取り入れます。YOASOBIの「アイドル」もそうでした。最初はアニメの主題歌ですが、ダンスやショート動画に使われて爆発的に広がり、海外でもヒットしました。曲の寿命を延ばしているのはリスナー自身なのです。
スイーツでも同じことが起こっています。「マリトッツォ」はインスタの一枚の写真から火がつき、コンビニに並びました。「カヌレ」も若者が「映える」と投稿したことからリバイバルブームが来た例です。企業はSNSの投稿を見て「あ、次はこれが売れそうだ」と動きます。
つまり、今の時代は「マーケティングを計画するよりも、SNSを観察するほうが早い」という逆転劇が起きているのです。
Z世代の「遊び心」が経済を動かす
なぜZ世代からこれだけ新しいトレンドが出てくるのか。それは「遊び心」がベースにあるからです。
TikTokの「#うっせぇわ」チャレンジを思い出してください。最初は歌をふざけて口パクする動画でした。それがあまりに楽しそうなので真似する人が続出。結果的に曲が社会現象になり、紅白歌合戦まで登場しました。
Instagramでも「クリームソーダ色」という謎の表現が流行りました。最初は青と緑の中間くらいの色を「クリームソーダっぽい」と投稿した女子高生から始まりました。するとアパレルブランドがその言葉をキャッチして、新作のカラー名に採用。Z世代の遊び心が、実際の売上につながってしまったのです。

ぼくはこの現象を見て「Z世代は無邪気に遊んでいるだけなのに、その遊びが経済のエンジンになっている」と感じます。マーケティングを学んだ社会人よりも、楽しんで発信する学生の方が世の中を動かしているのです。
まとめ
Z世代がSNSで発信する言葉やアイデアは、単なる「若者のノリ」ではなく、文化をつくり、経済を動かしています。
「ぴえん」から始まったゲームや商品化、「おしゃピク」から生まれた雑貨市場、TikTokのダンス動画から爆発的に広がる音楽ブーム。どれも、企業が仕掛けたものではなく、ぼくらユーザーが自然に楽しんでいる遊び心から誕生しました。
これからは「テレビや雑誌が流行を決める時代」ではなく「SNSでぼくらが遊びながら流行をつくる時代」です。ぼくたちの一言や一枚の写真が、次のトレンドを作る可能性を秘めているのです。
次にあなたがSNSに投稿する一言も、明日の流行語かもしれません。そう考えると、SNSってただの暇つぶしどころか、未来の文化を生み出す遊び場なんだなあとワクワクしてきます。

[文責:勅使河原ハルト]

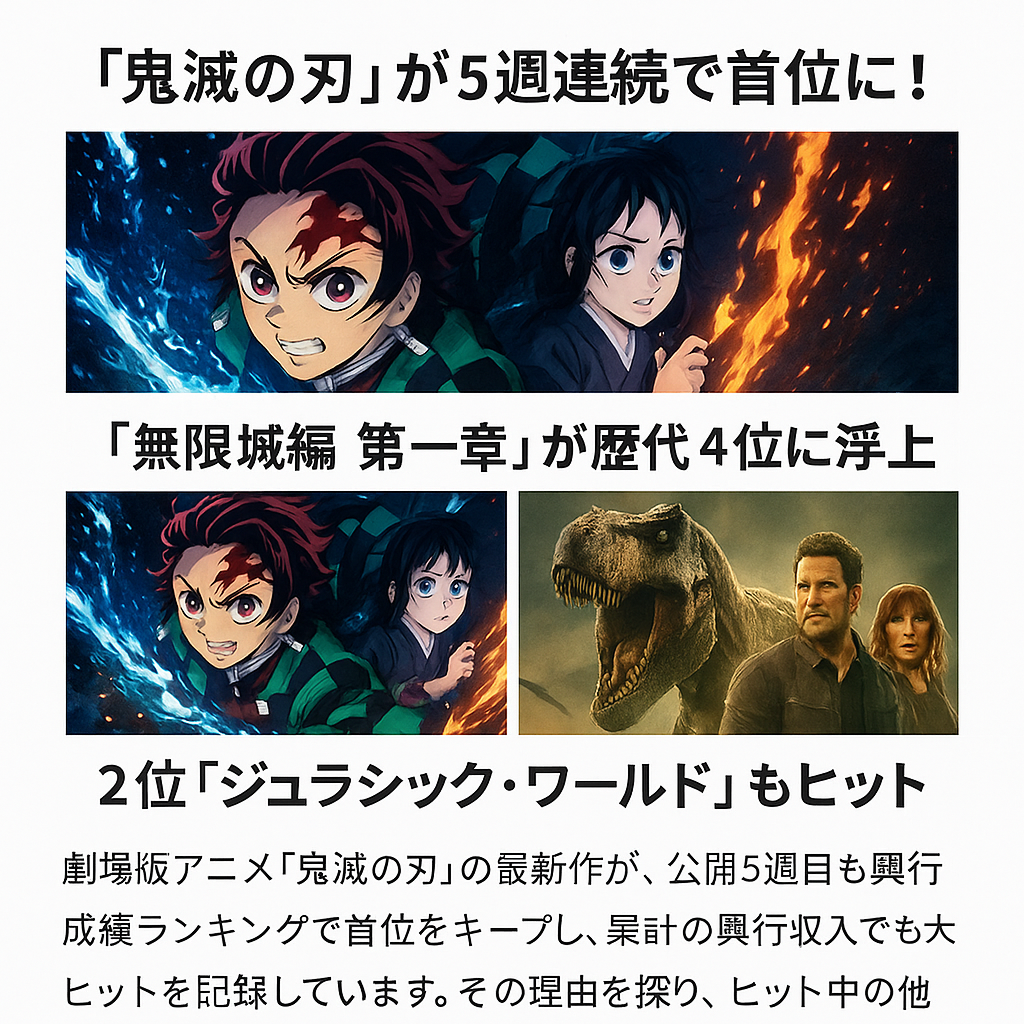

コメント