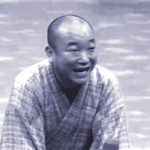 桂枝雀(二代目)
桂枝雀(二代目) ★桂枝雀(二代目)あくびの稽古(あくび指南)
『あくび指南』とは古典落語の演目の一つである。主な噺家は柳家小せんなどがいる。
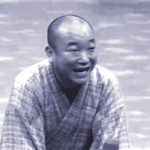 桂枝雀(二代目)
桂枝雀(二代目) 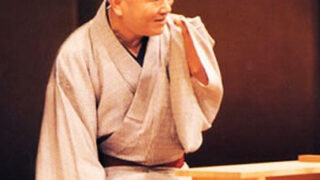 桂枝雀(二代目)
桂枝雀(二代目) 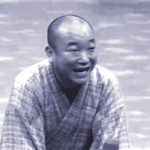 桂枝雀(二代目)
桂枝雀(二代目) 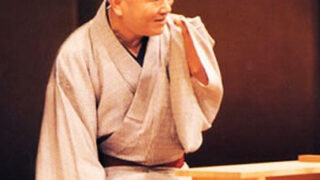 桂枝雀(二代目)
桂枝雀(二代目) 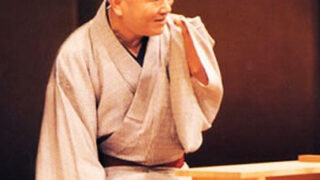 桂枝雀(二代目)
桂枝雀(二代目) 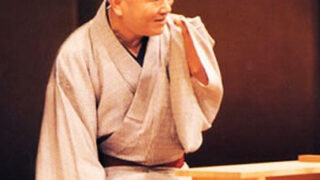 桂枝雀(二代目)
桂枝雀(二代目) 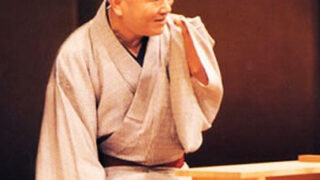 桂枝雀(二代目)
桂枝雀(二代目) 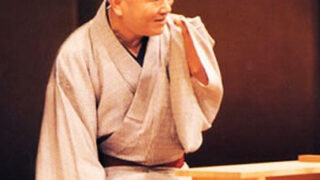 桂枝雀(二代目)
桂枝雀(二代目)  立川談志
立川談志  三遊亭圓生(六代目)
三遊亭圓生(六代目)  三遊亭圓生(六代目)
三遊亭圓生(六代目)  三遊亭圓生(六代目)
三遊亭圓生(六代目)  三遊亭圓生(六代目)
三遊亭圓生(六代目)  三遊亭圓生(六代目)
三遊亭圓生(六代目)  三遊亭圓生(六代目)
三遊亭圓生(六代目)  三遊亭圓生(六代目)
三遊亭圓生(六代目)  三遊亭圓生(六代目)
三遊亭圓生(六代目)  柳家小さん(五代目)
柳家小さん(五代目)  三遊亭金馬(三代目)
三遊亭金馬(三代目)  柳家三三
柳家三三