 立川談志
立川談志 ★立川談志/五人廻し
上方ではやらないが、吉原始め江戸の遊廓では、一人のおいらんが一晩に複数の客をとり、順番に部屋を廻るのが普通で、それを「廻し」といった。これは明治初めの吉原の話。売れっ子の喜瀬川おいらん。今夜は四人もの客が待ちぼうけを食ってイライラし通しだが...
 立川談志
立川談志  立川談笑(六代目)
立川談笑(六代目)  金原亭馬生(十代目)
金原亭馬生(十代目)  立川談志
立川談志  桂文楽(八代目)
桂文楽(八代目)  桂文楽(八代目)
桂文楽(八代目) 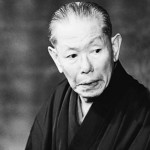 林家彦六(八代目 林家正蔵)
林家彦六(八代目 林家正蔵) 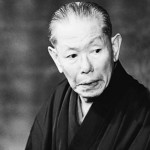 林家彦六(八代目 林家正蔵)
林家彦六(八代目 林家正蔵)  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  柳家小さん(五代目)
柳家小さん(五代目)  露の五郎兵衛(二代目)
露の五郎兵衛(二代目) 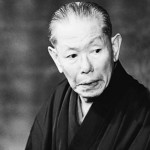 林家彦六(八代目 林家正蔵)
林家彦六(八代目 林家正蔵) 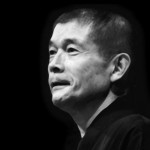 柳家小三治(十代目)
柳家小三治(十代目) 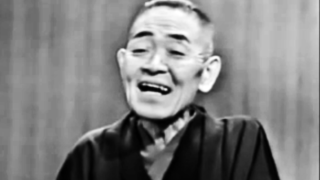 三笑亭可楽(八代目)
三笑亭可楽(八代目)  古今亭右朝
古今亭右朝  古今亭右朝
古今亭右朝  三遊亭圓橘(三代目)
三遊亭圓橘(三代目)  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  露の五郎兵衛(二代目)
露の五郎兵衛(二代目)