 古今亭今輔 (五代目)
古今亭今輔 (五代目) ★古今亭今輔(五代目)ねぎまの殿様
三太夫を連れて向島の雪見にお忍びで出掛けた。本郷三丁目から筑波おろしの北風の中、馬に乗って湯島切り通しを下って上野広小路に出てきた。ここにはバラック建ての煮売り屋が軒を連ねていた。冬の寒い最中でどの店も、”はま鍋”、”ねぎま”、”深川鍋”な...
 古今亭今輔 (五代目)
古今亭今輔 (五代目)  古今亭今輔 (五代目)
古今亭今輔 (五代目)  古今亭今輔 (五代目)
古今亭今輔 (五代目)  三遊亭圓楽(五代目)
三遊亭圓楽(五代目)  春風亭柳枝(八代目)
春風亭柳枝(八代目)  三遊亭金馬(三代目)
三遊亭金馬(三代目) 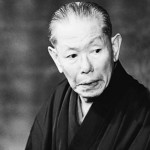 林家彦六(八代目 林家正蔵)
林家彦六(八代目 林家正蔵) 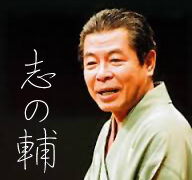 立川志の輔
立川志の輔  桂雀々
桂雀々 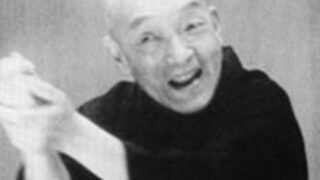 三遊亭百生(二代目)
三遊亭百生(二代目)  桂文治(九代目)
桂文治(九代目)  春風亭柳好(三代目)
春風亭柳好(三代目)  柳家小さん(五代目)
柳家小さん(五代目)  柳家喬太郎
柳家喬太郎  立川談志
立川談志 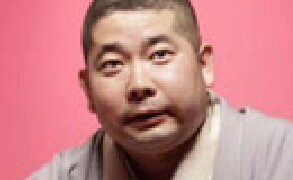 桃月庵白酒
桃月庵白酒 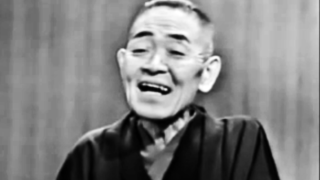 三笑亭可楽(八代目)
三笑亭可楽(八代目) 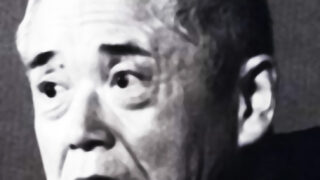 桂文治(十代目)
桂文治(十代目)  立川談志
立川談志  桂文楽(八代目)
桂文楽(八代目)