七代目金原亭馬生時代の音源:昭和10年(1935年)2月発売SP盤(当時44歳)
七代目金原亭馬生襲名:1934年(昭和9年)
五代目古今亭志ん生襲名:1939年(昭和14年)
あらすじ
氏子中(うじこじゅう)
ある日、商用で出かけた亭主が出先から帰宅すると、女房の腹が膨れている。
問い質すと女房は、日頃から子どもが欲しいと氏神の神田明神に毎日参ったゆえ授かったと、いけしゃあしゃあと話す。亭主は女房の浮気を疑い、その相手を探そうと出産後、氏子連中を集めて*胞衣(えな)を洗う。そうすると胞衣に、「神田大明神」と現れたのも束の間、その傍には「氏子中」と文字が出る……
※胞衣=胎児をつつんでいる膜と胎盤
解説
この演目は、もともと「町内の若い衆」という題で口演されるのが通例になっている。分量としては一席の落語というより、やや長めの小噺といった趣きで、艶笑小噺に分類される類の話にあたる。
昭和9年(1934年)9月、当時44歳だった志ん生は、古今亭志ん馬から七代目金原亭馬生を継ぎ、上野鈴本演芸場で襲名披露を行っている。その翌年の2月には、日本ビクター蓄音機から「氏子中(うじこじゅう)」がSPレコードのAB面として発売されており、この音源は「五代目 古今亭志ん生」ではなく、「七代目 金原亭馬生」と表記するのが正確ということになる。
五代目古今亭志ん生を正式に襲名するのは、それから5年後の昭和14年(1939年)3月1日。披露の場は再び鈴本演芸場で、この襲名以降、志ん生の名は広く知られていくことになる。昭和16年(1941年)2月には神田花月にて定例の独演会も始まり、50歳にしてようやく噺家としての生活が安定を見せるようになっていく。
一方、志ん生より10歳年下の六代目橘家圓蔵は、昭和16年5月に六代目三遊亭圓生の名を継ぎ、三遊派の代表格として名乗りを上げる。しかし、子供落語の橘家圓童時代から数えて芸歴30年を超えていたとはいえ、当時まだ40歳。先代圓生という後ろ盾を失ったこともあり、若かりし品川圓蔵門下時代の勢いに比べると、目立った活躍があったとは言いがたい。真に三遊派の屋台骨として活躍するようになるのは、昭和30年(1955年)、55歳を迎えて以降のことになる。
時は流れ、戦争も終盤に差しかかった昭和20年(1945年)5月、志ん生と圓生は慰問団の一員として新潟から大陸へ渡ることになる。東京では連日の空襲が続き、防空壕に避難するのが日常化していたため、寄席興行どころではなかった。志ん生は特に臆病な性格だったようで、空襲警報が鳴るたびに家族を置き去りにして逃げ出す姿があったと伝えられている。
さらに当時の東京では物資不足が深刻で、配給制の下、好物の酒さえ手に入りづらい状況だった。そんな折、「満州にはまだ酒がある」と聞けば、普段は東京を離れることを嫌がっていた志ん生も、空襲のない満州行きを選ばざるを得なかったのだろう。現地で慰問興行の手配をしていたのが、当時放送局アナウンサーだった森繁久彌で、後年になってこう語っている。「志ん生師匠は、とにかく酒ばかり飲んでいて、肝心の落語をろくにやってくれなかった」と。
この一件は、志ん生という人物の本質をよく表している。どのような場でも真摯に高座へ向き合う圓生とは対照的に、志ん生には慰問先で落語を語ろうという意識は最初から薄かったと見られる。
志ん生が満州に渡った理由を突き詰めれば、空襲を避けて、酒がある場所へ逃れただけとも言える。彼にとって落語とは、寄席に足を運んでくれる客の前で語るものであり、たとえ戦時中であっても、自ら赴いて誰かに聴かせるようなものではない、という強い信念を持っていたようだ。その揺るぎない価値観があったからこそ、戦後には誰の追随も許さぬ存在へと成長していったのかもしれない。
[出典:https://jbmbkyo.blog.fc2.com/blog-entry-3399.html]
豆知識
胞衣を洗う習俗を示す言葉の一つに、「アライゴ」がある。
父が不詳で子どもが産まれた場合、誰が父であるかを見定めるために胞衣を洗い、そこに浮き出る「紋」を見るという習俗が近世期にあった。
胞衣を洗われた子どもは成長の後に、「アライゴ」(胞衣を洗って父が誰であるかを見定めた子)と呼ばれた。
『日本産育習俗資料集成』にも胞衣を洗って父の紋を見るという習俗が報告されており、また、各地に胞衣を洗うと子どもの前世がわかるという俗信が伝えられている。
胞衣を洗うことは、落語のネタとなるほど世俗の間で広く行われていた習俗だった。
現代のように遺伝子レベルで父親を確定することができない近世期、胞衣は子どもの出自を明らかにする役目を担っていた。
[出典:胞衣にみる産と育への配慮-近世産育所における子どもと母の関係]
「胞衣(えな・ほうい)」とは何か
出産の際、赤ちゃんとともに排出される「胎盤」「へその緒」、そして胎児を包んでいた卵膜などをひとまとめにして「胞衣(えな)」と呼ぶ。別名「胎衣(たいえ)」とも書かれ、古くから日本では神聖視されてきた。
信仰と風習:胞衣を埋める意味
かつて日本では、胞衣は子どもの命とつながる重要な存在と捉えられており、「胞衣納め」と呼ばれる儀礼的な埋納が各地で行われていた。地域によってやり方は異なるが、胎盤などを壺に納めて地中に埋めたり、神社に奉納したりすることで、子どもの無事な成長や将来の出世を祈願する風習があった。
埋納される場所にも意味が込められていた。例えば、人が頻繁に通る土間や建物の下など、人の気が集まる場所に埋めることで、子どもが健やかに育つと信じられていた。また、壺の中には胎盤と一緒に銭貨、筆、墨、刀子(ナイフ)などの小物が入れられることもあり、特に筆や墨は、学問や役人としての将来を願う象徴とされた。
変わりゆく風習と現代の扱い
このような胞衣の埋納は、奈良時代にはすでに存在していたが、明治以降、西洋医学の導入とともに衛生に関する意識が大きく変わっていく。その結果、胞衣を土に埋めるという行為は不衛生とされ、次第に廃れていった。
現在では、いくつかの自治体で「胞衣条例」などが制定され、胎盤や臍帯の取り扱いについて具体的な指針が設けられている。また近年では、臍帯血の採取と保存が進み、白血病などの治療に使われる例も見られるようになった。医学の進歩とともに、胞衣はかつての呪術的な対象から、医療資源としての価値を持つ存在へと変わりつつある。
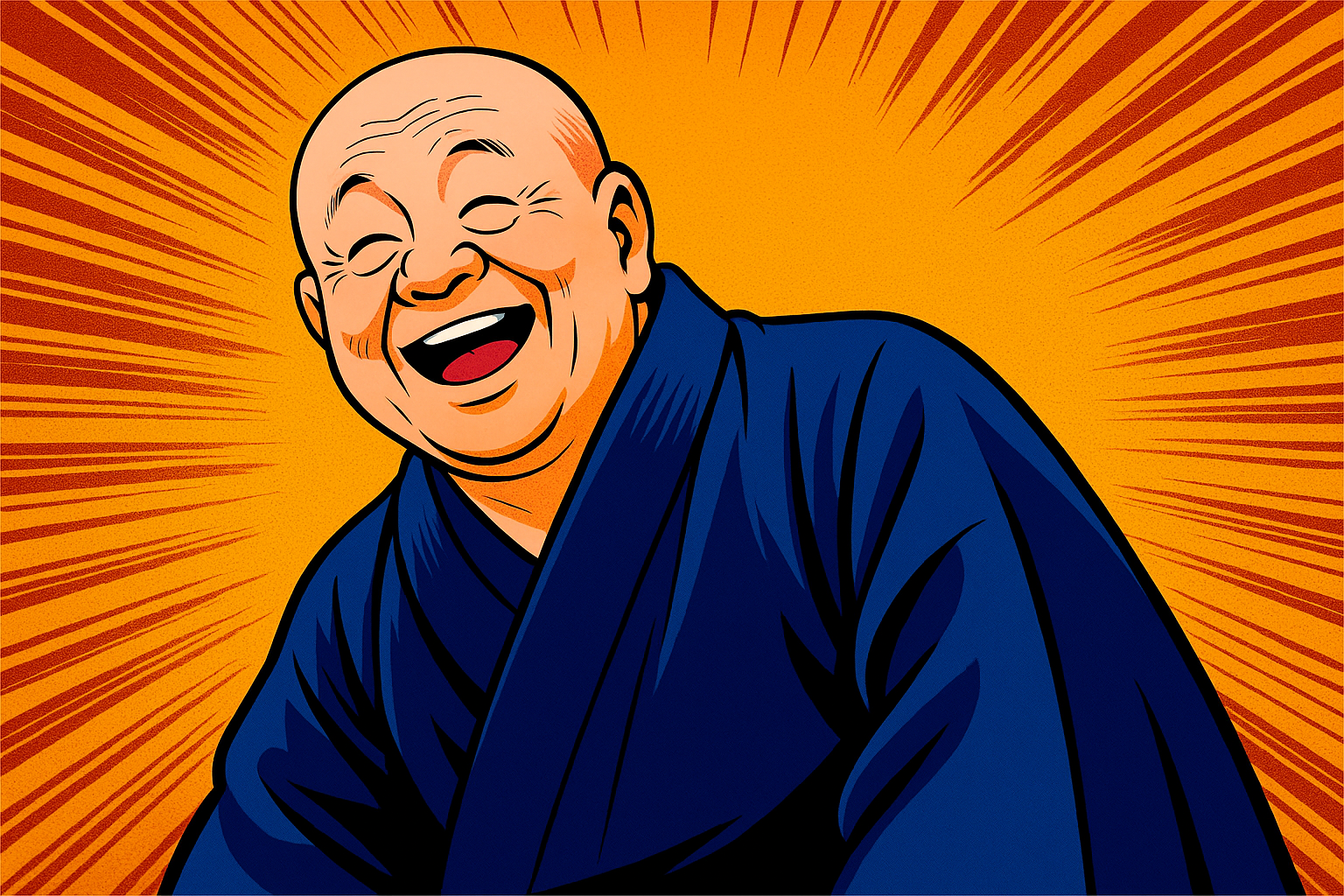


コメント