 古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目) ★古今亭志ん生(五代目)疝気の虫
疝気の虫(せんきのむし)は古典落語の演目の一つ。原話は、寛政8年に出版された笑話本・「即答笑合」の一遍である『疝鬼』。主な演者には、初代三遊亭遊三や5代目古今亭志ん生、桂雀々などがいる。あらすじ変な虫を見つけた医者。つぶそうとすると、なんと...
 古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  古今亭志ん朝
古今亭志ん朝  立川談志
立川談志  三遊亭圓遊(四代目)
三遊亭圓遊(四代目)  金原亭馬生(十代目)
金原亭馬生(十代目)  桂文楽(八代目)
桂文楽(八代目) 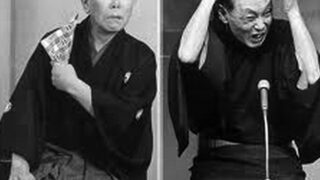 三遊亭圓生(六代目)
三遊亭圓生(六代目)  三遊亭圓生(六代目)
三遊亭圓生(六代目)  春風亭昇太
春風亭昇太  その他
その他  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  立川談志
立川談志 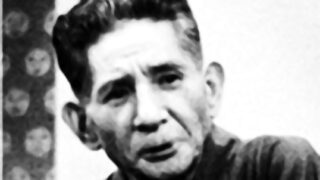 桂三木助(三代目)
桂三木助(三代目)  立川談志
立川談志  春風亭柳朝(五代目)
春風亭柳朝(五代目) 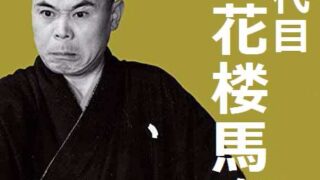 蝶花楼馬楽(六代目)
蝶花楼馬楽(六代目) 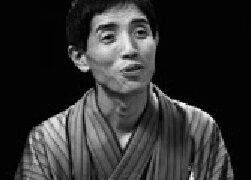 桂春蝶(二代目)
桂春蝶(二代目)  柳家権太楼(三代目)
柳家権太楼(三代目)  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  笑福亭松鶴(五代目)
笑福亭松鶴(五代目)