 古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目) ★古今亭志ん生(五代目)和歌三神(わかさんじん)
落語 古今亭志ん生 和歌三神俳諧の師匠が、雪が降ったので権助を連れて、向島へ雪見に行く。酒持参でどこかで飲もうとすると、土手の下で乞食が三人酒盛りをしている。酒を恵んでやると大喜び。自分の飲み分が無くなると言う権助をなだめて、したみ酒が無...
 古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目) 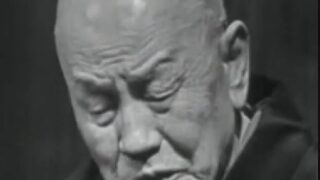 古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)  古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目)