 柳家三三
柳家三三 ★柳家三三/長屋の花見(貧乏花見)
長屋の花見は元々は上方落語で、貧乏花見という。3代目蝶花楼馬楽、4代目柳家小さん、5代目柳家小さん、林家彦六、10代目柳家小三治の得意な演目である。
 柳家三三
柳家三三 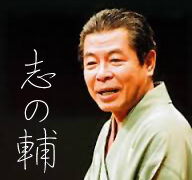 立川志の輔
立川志の輔 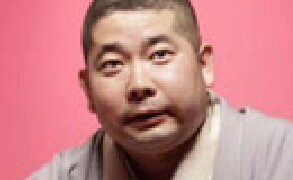 桃月庵白酒
桃月庵白酒  柳家小さん(五代目)
柳家小さん(五代目)  柳亭痴楽(四代目)
柳亭痴楽(四代目)  柳亭痴楽(四代目)
柳亭痴楽(四代目)  柳家小さん(五代目)
柳家小さん(五代目)  柳家喬太郎
柳家喬太郎  鈴々舎馬風(四代目)
鈴々舎馬風(四代目) 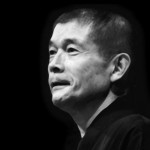 柳家小三治(十代目)
柳家小三治(十代目)  柳家三三
柳家三三 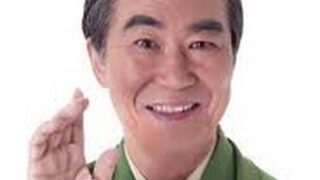 桂文枝(六代目)
桂文枝(六代目)  柳家権太楼(三代目)
柳家権太楼(三代目)  笑福亭松鶴(六代目)
笑福亭松鶴(六代目) 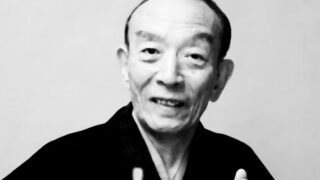 桂歌丸
桂歌丸  柳家小さん(五代目)
柳家小さん(五代目) 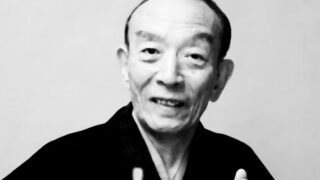 桂歌丸
桂歌丸  コラム
コラム 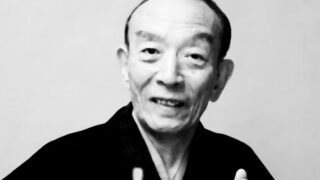 桂歌丸
桂歌丸 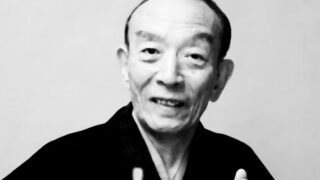 桂歌丸
桂歌丸