 林家三平
林家三平 rakugochan
 林家三平
林家三平  柳家小さん(五代目)
柳家小さん(五代目) ★立川談志/浮世根問
浮世根問(うきよねどい)、または無学者論として知られるこの古典落語は、知識を誇示することの空虚さをユーモラスに描いた作品です。もともとは江戸時代のエピソード「根問」に由来し、似たような話として「薬缶」という話もあります。この話の主要な演者に...
 古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目) ★古今亭志ん生(五代目)三味線栗毛#846-0114
あらすじ老中筆頭、酒井雅楽頭(さかいうたのかみ)の次男坊・角三郎は、ちょくちょく下々に出入りするので親父から疎んじられ、五十石の捨て扶持をもらって大塚鶏声ヶ窪の下屋敷で部屋住みの身。そうでなくとも次男以下は、養子にでも行かない限り、一生日の...
 春風亭柳枝(八代目)
春風亭柳枝(八代目) ★春風亭柳枝(八代目)かつぎや
 三遊亭金馬(四代目)
三遊亭金馬(四代目) ★【三遊亭金翁】三遊亭金馬(四代目)かつぎや
落語「かつぎや」三遊亭金馬かつぎやは、落語の演目の一つ。古典落語に分類される。かつぎ屋とも表記される。正月の商家を舞台にした噺。別題に『かつぎ屋五兵衛』『七福神』。もとは上方落語の正月丁稚(しょうがつでっち)。現在の冒頭部よりも前に、登場人...
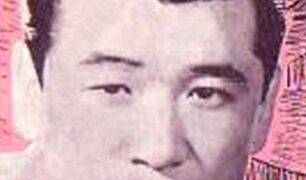 その他
その他 ★【貴重音源】フランク亭永井/夕立屋
フランク永井の師匠は 九代目入船亭扇橋
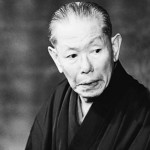 林家彦六(八代目 林家正蔵)
林家彦六(八代目 林家正蔵) ★林家彦六(八代目 林家正蔵)目黒のさんま#21614-0114
落語 「目黒の秋刀魚」 林家正蔵(彦六)目黒のさんま(めぐろのさんま)は落語の噺の一つである。さんまという下魚(低級な魚)を庶民的な流儀で無造作に調理したら美味かったが、丁寧に調理したら不味かった、という滑稽噺。落語界の中では秋の噺としてよ...
 柳家小さん(五代目)
柳家小さん(五代目) ★柳家小さん(五代目)言訳座頭
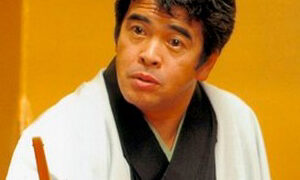 三遊亭歌之介
三遊亭歌之介 ★三遊亭歌之介/爆笑龍馬伝#131
落語 「爆笑龍馬伝」 三遊亭歌之介
 三遊亭圓楽(五代目)
三遊亭圓楽(五代目) ★三遊亭圓楽(五代目)阿武松(おうのまつ)#102
あらすじ京橋観世新道に住む武隈文右衛門という幕内関取の所に、名主の紹介状を持って入門してきた若者がある。能登国鳳至(ふげし)郡鵜川村字七海の在で、百姓仁兵衛のせがれ長吉、年は二十五。なかなか骨格がいいので、小車というしこ名を与えたが、この男...
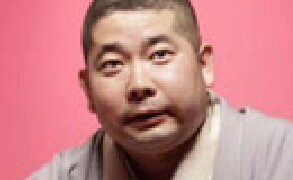 桃月庵白酒
桃月庵白酒 ★桃月庵白酒/富久#128
 柳家喬太郎
柳家喬太郎 ★柳家喬太郎/冬のそなた#99
 三遊亭金馬(三代目)
三遊亭金馬(三代目) ★三遊亭金馬(三代目)転失気(てんしき)#172
体調のすぐれない和尚が診察に訪れた医者から「てんしき」があるかないかを聞かれる。和尚は知ったかぶりをしてその場をごまかし、あとで小僧を呼んで近所に「てんしき」を調べに行かせる。だれもが知ったかぶりをしたため、はっきりしたことを聞き出せない小...
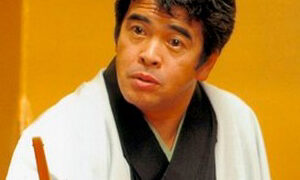 三遊亭歌之介
三遊亭歌之介 ★三遊亭歌之介/桃太郎
三遊亭歌之介 「桃太郎」『桃太郎』(ももたろう)は、落語の演目の一つ。短く登場人物も少ないので手軽にやれる噺として上方、東京ともに多くの演者がある。3代目桂春団冶は「いかけ屋」のマクラに演じている。あらすじ昔話を親が語る傍らで子供が寝入って...
 古今亭志ん生(五代目)
古今亭志ん生(五代目) ★古今亭志ん生(五代目)ぼんぼん唄
★古今亭志ん生(五代目)ぼんぼん唄江戸時代、京橋八丁堀玉子屋新道に源兵衛という背負い小間物屋があった。彼と妻のおみつは子宝に恵まれず、二人の静かな暮らしは、その欠けた喜びによって影が差していた。子どもを切望する源兵衛は、おみつの勧めで浅草観...
 林家正蔵(七代目)
林家正蔵(七代目) ★林家正蔵(七代目)按摩小僧(あんま小僧)#191
 春風亭柳枝(八代目)
春風亭柳枝(八代目) ★春風亭柳枝(八代目)堪忍袋
落語 「堪忍袋.」 春風亭柳枝
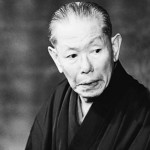 林家彦六(八代目 林家正蔵)
林家彦六(八代目 林家正蔵) ★林家彦六(八代目 林家正蔵)毛氈芝居(もうせんしばい)
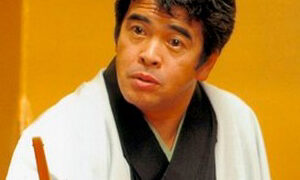 三遊亭歌之介
三遊亭歌之介 ★三遊亭歌之介/竹の水仙
落語 「竹の水仙」 三遊亭歌之介竹の水仙(たけのすいせん)は、落語の演目の一つ。名人と呼ばれた大工・左甚五郎を主人公とした噺である。主な演者には、桂歌丸や、5代目笑福亭枝鶴などがいる。
 春風亭柳橋(六代目)
春風亭柳橋(六代目) ★春風亭柳橋(六代目)天災
長屋に住む男(東京では八五郎)は、短気で喧嘩っ早く、ある日も妻を殴り、止めに入った母親を蹴飛ばして、その足で隠居のところへ転がり込み、家庭の不満をこぼす。あきれた隠居は、「お前はもっと穏やかな人間にならなければならない。紅羅坊奈丸(べにらぼ...